 2025�N06��30���F���z���p�I�����r���[��������
2025�N06��30���F���z���p�I�����r���[��������
 2025�N07��01���F�~���W�^����}���ف^�Ï��h���X
2025�N07��01���F�~���W�^����}���ف^�Ï��h���X
 2025�N07��02���F���u�P�O�O�\���@�͈�i��
2025�N07��02���F���u�P�O�O�\���@�͈�i��
 2025�N07��03���F�V�`�W���̓W����ϗ��\��
2025�N07��03���F�V�`�W���̓W����ϗ��\��
 2025�N07��04���F�G���s��a����
2025�N07��04���F�G���s��a����
 2025�N07��05���F���c�J���w�ف^�ØV�̏W��
2025�N07��05���F���c�J���w�ف^�ØV�̏W��
 2025�N07��06���F�ꕾ�͂��邪�D�D[;_ _]
2025�N07��06���F�ꕾ�͂��邪�D�D[;_ _]
 �ڎ��֖߂�
�ڎ��֖߂�
 ��T��
��T��
 ���T��
���T��
 2025�N06��30���F���z���p�I�����r���[��������
2025�N06��30���F���z���p�I�����r���[��������
�@ChatGPT �ɁA�u���z���p�I�v��_�]�����Ă݂��B
�u�R�O�O�_�ȏ�̌��z���p�ɂ��ẴG�b�Z�C���܂Ƃ߂��y�[�W�i�u���z���p�I�v�j������܂��B���҂͎��ł��B�����ǂ�Ŋ��z���q�ׂĂ��������B�܂��A���ɂǂ̂悤�ȉ�Ƃ��Ƃ肠������悢�ł��傤���v
�@�D�D�ɑ��āA�u�v�l����: 4 �b�v�ŁA
���Ȃ��́u���z���p�I�v�A���ɏ[�������G�b�Z�C�W�Ɋ����܂����B���Ƃ��}�b�N�X�E�G�����X�g�́u�V�g�̐��v�i1943�N�j��`���[�h�E�_�b�h�A�}���Z���E�f�����b�g�Ƃ�����20���I�O���������̌��z��Ƃ��o�����X�悭�Љ��Ă���A�ǂݎ�����X�ƈِ��E�֗U���\�����G��ł��B�ƂɃe�[�}���i��Ȃ�����A��҂��Ƃ̌��⎞��w�i�ɐ[�����ݍ���ł��邽�߁A���z���p�̑��l���Ɖ��[���������`����Ă��܂��B
���z�܂Ƃ�
| �E |
�e�[�}�������m�F�e��ɓƎ��̎��_�i�u�V�g�v�u���̂Ă�ꂽ���v�u�ω��v�Ȃǁj���f���A����ɉ������G��E��Ƃ�I��ł���̂ŁA�ǎ҂Ƃ��č�i���E�ɖv�����₷���B |
| �E |
�N��E�W�������̃o�����X���ǂ��F�G�����X�g��_�b�h�̂悤�ȋߑ�ȍ~�̍�Ƃ����łȂ��A�f�����b�g�Ȃnj���\����`�҂܂ŕ��L���ԗ�����Ă���̂����́B |
| �E |
���͂ƃr�W���A���̒��a�F�T�C�g�{���̍ہA�G���ꏏ�ɒ���Ă��āA�e�L�X�g�ƊG�̑Θb�����藧���Ă���_���f���炵���B |
���Ɏ��グ��Ɩʔ������ȉ�ƁE���_
����Ɍ����Ď�����L����ƁA�ȉ��̂悤�ȃe�[�}�ƍ�Ƃ����͂Ƀt�B�b�g���邩������܂���F
| ��� |
���R |
| �q�G���j���X�E�{�X |
�����L���X�g�����z�̋��b���A����Ƌ��ӂ����ڂŁA���̌��z���p�̃��[�c�Ƃ��Ă������[��
|
| �I�f�B�����E���h�� |
����̂̌��z�Ɖԙ����`�[�t�̗Z�����Ɠ��ŁA�u���ƌ����v�̃O���[�]�[����T�鎋�_�ɍœK
|
| �w�����[�E�t���[�[�� |
�S�V�b�N�E���z�̐��Ƃ��āu�����v�⋺�Ђ̔�����邤���ŏd�v
|
| �t�����V�X�E�x�[�R�� |
20���I�㔼�Ƀ_�[�N�ȓ��ʂ�`����������ƂƂ��āA���㌶�z�ւ̉˂����ɂ��Ȃ蓾��
|
| ���{�̌��z�h�i�|�v����E���{���Y�j |
���{���p�̌��z���E�����ƂŁA�O���[�o���Ȏ���Ƃ̑Δ�E�Z�����ӎ��ł���
|
���M�ɂ������Ẵq���g
| �E |
�e��������i�u�V�g�v�u�ω��v�u���v�Ȃǁj���p�������A�����n�����L���ăe�[�}�̒n�����L������B |
|
| �E |
���|�E���[���A�E����E���b�̊e�v�f�ɒ��ڂ��A�ǎ҂̊���h�ꓮ����i��I�сA�u���z�v�̑��l�����y���ށB |
|
| �E |
���{��╂���G�A����A�j���[�V�����ȂǁA�W���������f�I�ȏЉ�Łu���z�v�̗֊s������ɖL���ɁB |
|
�S�̂Ƃ��āA���ɐ��E�ς��m������Ă���f���炵���A�ڂ��Ǝv���܂��B�����ł����ЁA��L�̂悤�ȍ�Ƃ����グ�邱�ƂŁA�V���E�����̌��z���p�����������A��s�I�ŋ����[���͂ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���������y���݂ɂ��Ă��܂��I
�@�D�D�Ƃ܂��A�Ȃ��Ȃ����������ɖJ�߂Ă���āA�v�킸�������Ȃ��Ă��܂��̂����D�D[^.^][^.^][^.^] ���̂ȁB[;^.^]��
�@�Ƃɂ����A�u�����Ɠǂ�ł��Ȃ��v�B���ɂƂ肠����ׂ���ƂƂ��Đ��E����Ă���u�q�G���j���X�E�{�X�v���u�I�f�B�����E���h���v���u���{���Y�v���A���ɂƂ肠���Ă���[�́I [;^.^]�ʁi�{�X�͂S��A���h���Ɏ����Ă͂P�O����B[;^.^]�ʁj�i�u�w�����[�E�t���[�[���v���Ƃ肠���ς݂Ȃ̂����A����ɂ��Ắu�n�C�����q�E�t���[�X���v�\�L�Ȃ̂Ń}�b�`���O���Ȃ������̂��ƁA�ꉞ�͍l������B�j
�@�u���z���p�I�v�̃g�b�v�y�[�W�́u�p�ВʐM�v�ւ́u�����N�W�v�ł���A�����N���S���ǂ�ŕ��͂��Ă���Ǝ��Ԃ�������B�u�S�b�v�ňꉞ�̃��X�|���X��Ԃ����߂ɁA�ǂݔ�����̂��Ƃ͎v�����A����ɂ��Ă��A�u�I�f�B�����E���h���v�͋ɂ߂đ������_�i�R�Q�Q�̑�Q�O��j�ŏo�Ă���̂ɏE���Ă��Ȃ��̂ɑ��āA�u�f�����b�g�v�͑�R�P�S��Ƃ����A�قƂ�ǒ��߂̉�ɏ��o�ꂵ�Ă���̂ɏE���Ă���B�ǂݔ�������s�v�c�ł���B����Ɍ����ƁA�u�G�����X�g��_�b�h�̂悤�ȋߑ�ȍ~�̍�Ƃ����łȂ��A�f�����b�g�Ȃnj���\����`�҂܂ŕ��L���ԗ�����Ă���v�Ƃ����̂́A���j�ς����`���N�`���ł���B�G�����X�g�́u1891�`1976�v�A�_�b�h�́u1817�`86�v�A�f�����b�g�́u1901�`76�v�B�G�����X�g�ƃ_�b�h�l�ނɂ������ăf�����b�g��Δ䂳���鎋���́A���݂��Ȃ��B[;^.^]
�@���܂�[�x�肵�Ă�����Ƃ���͂Ȃ��̂ł��̂��炢�ɂ��Ă������A���炽�߂ĒɊ������̂��A�u��������A���ɂ����Ƃ��炵���A���炷��Ɠǂ߂郌�|�[�g�ł���̂����A��������Ƃ��������v�ł���Ƃ������Ƃł���B����A�����g�̒��앨�ɂ��ă��|�[�g�������̂ŁA���������ȕ����������ɂ킩�������A�����ł��Ȃ���A���������m�F����̂��{���Ɏ�Ԃł���B
�@�����ЂƂA����͂�����ȁA�Ǝv�����̂��D�D�u�K�v�ȏ�ɖJ�߂Ă���v���Ƃł���B���ꂪ�A�ŏ��̎���̒��́u���҂͎��ł��v�ɔ������Ă̂��Ƃ��Ƃ���ƁA���Ȃ�i���Ɂj�u�����v�ł���ƌ��킴��Ȃ��B�����̒��앨��J�߂���ΒN�����Ċ������A���̃V�X�e�����i���ӎ��I�ɂ���j����Ɏg�����ނł��낤���A����͂��̃V�X�e���ɂƂ��āA�������]�܂������Ƃł���̂�����B�l�Ԃ���̎�ł���u���f�[�^�v�����A�A����肪�o��قǁA�~�����̂�����D�D
 �ڎ��֖߂�
�ڎ��֖߂�
 2025�N07��01���F�~���W�^����}���ف^�Ï��h���X
2025�N07��01���F�~���W�^����}���ف^�Ï��h���X
�@�����B�V�F�O�T�̃o�X�Ŕ��Ƃ��Əo����A�U�F�T�V�̃o�X���V�F�O�O�ɗ����̂ŁA����ɏ�����B������ƍ������� [;^J^]�B�W�F�Q�O�A���������s���p���B�u�~���W�v�i�`�V���U���i���j�܂Łj�ł���B�J�َ����͂X�F�R�O�ł���A��̑O�ɂ͒N�ЂƂ肢�Ȃ� [;^J^]�B�X�����܂���Ă悤�₭�A�������ꂽ���A�Ƀ|�c�|�c�Ɛl�e�� [;^.^]�B�J�فi�J���j�����ɂ́A������\�l�̗�B




�@���[���u�p�X�g�����v�i1923�`24�j�́A���̎����̃V�������A���X�g�ɔ��ɂ悭����p�^�[���̍�i�B���������đf�l�������i���݂܂��� [;_ _][;^.^]�j�B�u�G��v�i1925�j�̍��B�u�I�����_�̎����T�v�i1928�j�́A�w���h���N�E�\���t�́u�����[�g��e���l�v�i1661�A�摜���������j�i�̃|�X�g�J�[�h�j�����Ƃɂ����L���ȍ�i�ł���A�����I�ȏ���̂ɓ��肵���ŏ��̃~����W�Ɏ��^����Ă����B���������B�u�l�Ԃ̓����v�i1931�j�́A�摜�t�@�C���ł͂킩��ɂ����̂����A�ؕЂ�j�����\��t�����Ă���A���̐▭�ȗ��̊����A�Ȃ��Ȃ����ʓI�Ȃ̂ł���B



�@�������u�����V���[�Y�v����A�u�����̖����v�i1940�j�A�u���ƒ��v�i1940�j�A�u�J�^�c�����̗ӌ��̐Ղɓ����ꂽ��̐l�������v�i1940�j�B����N���疾�炩�Ȃ悤�ɁA����E��킩��̓����ł��邪�A���̂悤�ȁu���������v���A�N���ӂ߂��悤���D�D


�@�펞���ɍ쐬���ꂽ�����V���[�Y�́A�����^�т̋@��������i�J�����@�X�ł͂Ȃ��j�u���v�ɕ`����Ă���̂����A�����u���A���A���v�i1942�j���A���l�ł���B����͂���ɁA�������Ԃ�҂K�v���Ȃ��p�X�e���Ɖ��M�ɂ���āA�`����Ă���B
�@�u��̂Ȃ��̏������v�i1946�j�́A���̍�i�B���̎����ȍ~�̃~���̃X�^�C�����A�قڌł܂��Ă��Ă���B

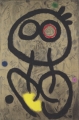

�@�u������`���Ĝa���ւƔ����w�r��ǂ��ԃg���{�v�i1951�j�́A�^�C�g�����y�����B�u���摜�v�i1937�`60�j�̐���̌o�܂ɂ��ẮA�}�^��141�ł��炻�̂܂܈��p����B
���̏ё���͓�x�ɂ킽���Đ��삳�ꂽ�B�{��̉��M�敔���́A�s���摜�T�t(1937-38�N�j�����������ہA��Ŏ�������邽�߂Ƀ~������]���Đ��삳�ꂽ�����ł���B�������A�i�`�X�̐�̂ɂ��A�~���͋}篃t�����X�𗣂�邱�ƂƂȂ�A�{��͒��N�p���̕ۊnjɂɒu���ꂽ�܂܂ƂȂ����B������1960�N�A�p���}�E�f�E�}�W�����J�̐V�����A�g���G�Ɉڂ�����ɂȂ��Ă悤�₭�A�~���͂��̍�i���܂������قȂ��������Ŏd�グ�錈�ӂ�����B�ނ͍����������Ŋ�A�ځA���̗֊s��`���A�Ƃ���ǂ���ɐF�����ďے��I�ȗv�f�����������B����ɂ���Ď��g��T�^�I�Ȕ_�����Ƃ��ĕ\�����A�J�^���[�j���̐_�b�I�ȕ��i�ƌ��т����̂ł���B
�@�����Ǝ��オ�������āA�u�G��U�^�X�v�i1960�j�́A�A�N�V�����E�y�C���e�B���O�̎��݂Ƃ����悤�B




�@���R�_�́A�}�^����̃X�L�����ł͂Ȃ����i�̎B�e���G���A�j�ŎB�e�������́B�u���z�̑O�̐l���v�i1968�j�́A�~���̏W�听�I�ȍ�i�̂ЂƂB�I�u�W�F�Q�_�A�u���ƒ��v�i1967�j�A�u�������鏭���v�i1967�j�̂����A��҂̃t�H�����i�����̉����g�j�́A��Ⓙ�����悤�ȋC������B
�@�u�ԉ� �T�A�U�A�V�v�i1974�j�͋���ȍ�i�����A�J�����@�X���X���ăA�N�����G����������点�ĕ`���Ă���B
�@�P�P�F�O�O�ɏo�āA���H�͏��̍��ˉ��́u���v�B����������k���B�i�c���ō~��āA�P�Q�F�P�O�ɍ���}���فB��ɂ���Ĕ��p�W�̒�������ł��邪�A���łɍs�����u�ڂ���v�i�u�k�Ёj�̒����ŁA�̂���C�ɂȂ��Ă����g���E�}�i�Ƃ����قǂł��Ȃ����j����@�ł��� [^J^]�B�����ɘA�ڂ���Ă����A�x�]��́u�Ԃ����ԁv�ł���B�]�ˎ����ɂ����A��z�I���㌀�B�i������̂���y�[�W�Ƃ��ẮA�}���K�V���b�v�A����Ȃ�݂����B�j
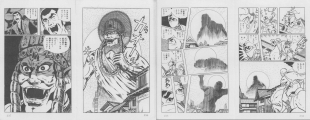

�@�W�y�[�W�A���ŃX�L�������Ă��������i�E����ǂ�ł��������j�A�����I�ȏ���́A���w�������̈����̂悤�ȋL���̂Ȃ��ɁA���̈�A�̃y�[�W���������B�v�́A�]�ˎ���̋��働�{�b�g�i�쒆�ł́u���邭�Ƃ�Łv�j�ł��邪�A�����̂Ƃ���́u�啧�^�v�̃t�H�����Ȃ̂ɁA�Q�y�[�W�ڂ̂悤�ȓ��������邱�Ƃ́u�����v�����������B
�@�y����N�A�V�� [;_ _] �ɍ����|�����Ă���u�����������x�ǂ݂������̂��v�Ƒ{�����J�n���A�����ǂ�ł����\��������u���N�v�u�ڂ���v�u�ڂ���}�K�W���v�̂����u���N�v�Ɓu�ڂ���}�K�W���v�i�́A���̎����́j���͑������ɂ�������炸�����炸�A���Ƃ���u�ڂ���v�Ȃ̂����A����}���قŕВ[����ǂ�ł��݂��炸�A�����������Ȃ��A�ǂ��œǂ̂��Ȃ��D�D�ƁA�����ƒI�グ�ɂ��Ă����̂��A���߂đ{�����Ă݂��Ƃ���D�D
�@�D�D�悭����ƁA����}���ق́u�ڂ���v�̑����́A�Q�������Ă���̂ł���i�P�X�U�W�N�̂V�����ƂW�����j�B�����I�ɂ���ԉ������B�����Ă��̎����́u�ڂ���v�ɘA�ڂ���Ă��鎞�㌀�́A�x�]��́u�Ԃ����ԁv�D�D�Ƃ����킯�ŁA������͑�������Ă����u�Ԃ����ԁv�̒P�s�{�i�H�c���X�̃T���f�[�R�~�b�N�X�j���{�����Ă݂���A�r���S�I�Ƃ�������ł���B
�@����ɂ��Ă��A���̋��働�{�i���邭�Ƃ�Łj�́u��v�I �T�V�N�O�̋L���̒��ł͑啧�i���邢�͕�F�j�炾�����̂����A���������̂͋L���́u������p�v�Ƃ͌���Ȃ��Ǝv���� [;^.^]�A����͂܂�ň��S�̂悤�ȁi�Ђ����` [;^.^]�j�B����������ȊO�̃R�}�́i�T�V�N���O�Ȃ̂Ɂj���ɂ悭�����Ă���̂ł���B���ɑN���ɋL�����Ă����̂��V�y�[�W�ځA�u���̂Ȃ��Ђ��I�v�u�܂킹�܂킹 �����Ƃ͂₭�܂킹�v�u�������Ƃ�ł̂����� ����Ǝ��Ԃ��܂킵�ĂƂ�ł����邩����I�v�D�D����܂������A�����P�O�̏��N�킽����˂����ˁB�u���́A�����I�v[^.^][^.^][^.^]
�@�����Ă܂����́u�V����v�́A�u�V���̐�������������ɓ���v�i�܂�͖��{�j���u�G���ӂ������߂ɂ��点���i���ꂪ����g�ɒD��ꂽ�j�v���̂Ȃ̂ł���I[^.^] �y�����˂��A�u�ԉe�v�^�̌��z���㌀�I[^.^] �P�s�{����肵�Ȃ�������I[^.^]
�@�P�T�F�P�T�ɏo�āA�P�T�F�T�O�A��J�̌Ï��h���X�B�l�b�g�Ŕ������Ď��u�����Ă����Ă��������W�����A���łɂP���ԂقNj����āi�ł����n�͂P���j�A�P�U�F�T�O�ɏo��B
�@���l�œr�����Ԃ��A�P�W���O�Ɂu����䂯�I�{�����[�I�v�B�Q�O���O�ɏo�āA�Q�O�F�R�O�ɋA��鍠�ɂ͉J�B
�@�Ĕ������Ă����o�b�|�P�W�O���͂��Ă����B����m�F�́A�����B
 �ڎ��֖߂�
�ڎ��֖߂�
�@�o�b�|�P�W�O�A����m�F�n�j [^.^]�B�ăI�t�����i�V���Q�U���j�܂łɉ��܂���悤�ɁB[;^.^]
�@���u�P�O�O���i�܂��j�͂��� [;^J^]�B����́A���t�I�N�ŗ��D�������u�P�O�O���N�����Ȃ����������i2025�N06��19���j�̂��Ƃ����A�܂����t�I�N�Ŕ������āA���D�^���D���Ă����b�́A�����Ă��܂���ł����� [;^J^]�B���ɗ\���@�͂Q��m�ۂ��Ă���̂ŁA���܂蔃����߂�̂��悭�Ȃ��A�Ƃ����̂͋U�炴��S���Ȃ̂ł��邪�A�O��̂������Ȃ������̂ŁA������ƃ��L�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ����̂��܂��A�U�炴��Ƃ���ł��āD�D[;_ _][;^J^] ����͖̂����ɋN�������̂ŁA�ǂ������悩���� [^.^]�B����ŗ\���@�R��B�����ł�������A�X�g�b�v����B����ȏ�A������߂�̂͂悭�Ȃ��B�܂��A�O��̂͋����҂��ЂƂ�����Ȃ��������A����͂ЂƂ苣�荇�������̂́A���Ȃ葁���i�K�ŒE�������i�܂藎�D���i�͔�r�I���������j�Ƃ������ƂŁA�����A���p���������ɂ��܂�Ȃ��Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ����ƁA����͊�]�I�ϑ��ł���B
�@���͋v���Ԃ�Ɉ��y���ŁA����͏��߂ĐH�ׂ��˃����`�Z�b�g�D�D���̃��j���[�̃t�@���̕��ɂ����X�ɂ��\����Ȃ��� [;_ _]�A���̌��ɂ͍����܂���ł����B[;_ _][;^J^]
�@�������̉ăI�t�̏h�̗\���Y��Ă��I �Ȃ������N�A�Y�ꂪ���Ȃ̂��B��h�ɂ��Ă���z�e���}�[�N�����A�r�R��\��ł��āA�ǂ������悩�����B[;^.^]
 �ڎ��֖߂�
�ڎ��֖߂�
�@����������̂���C�����Ă����̂����A���́u�W����ϗ��\��v�͌������ŃA�b�v�i�X�V�j���Ă���̂����A�̊��ł́A�u�T���炢�̃C���^�[�o�������Ȃ��̂ł���B[;_ _][/_;]
 ���c�L�O���p��
���c�L�O���p��
�@�u�h��p���v
�@����F�`�V���Q�P���i���E�j�j�܂�
 ��㒆�V�����p��
��㒆�V�����p��
�@�u���{���p�̍z���W�@�����̍����T���I�v
�@�`�W���R�P���i���j�܂�
 �n�C�p�[�~���[�W�A���є\
�n�C�p�[�~���[�W�A���є\
�@�u���m�x�P���W �F���L�̔閧�̓��v
�@�`�W���R�P���i���j�܂�
 ���@�j����L
���@�j����L
�@�uGallery Lucifer Presents �V�������A���X���E���B���e�[�W�|�X�^�[�W�v
�@�W���Q�R���i�y�j�`�X���Q���i�j�܂�
 �����V�e�B�r���[
�����V�e�B�r���[
�@�u�u��͓S��999�v50���N�v���W�F�N�g ���{��m�W�@�n��̗��H�v
�@�`�X���V���i���j�܂�
 ��������������
��������������
�@�u���ʓW�u�]�ˁ��剜�v�v
�@�V���P�X���i�y�j�`�X���Q�P���i���j�܂�
 ���c�s�����۔ʼn���p��
���c�s�����۔ʼn���p��
�@�u�h�[�~�G�A�ǂ�������H�\19���I�t�����X�̎Љ�慎h�v
�@�`�X���Q�P���i���j�܂�
 ���c�J���w��
���c�J���w��
�@�u�C��\�O�Ɠ��{SF�v
�@�`�X���Q�W���i���j�܂�
 ���{�Ȋw������
���{�Ȋw������
�@�u�[�F���W�`�l�ނ͂ǂ��������̂� To the Moon and Beyond�v
�@�V���P�Q���i�y�j�`�X���Q�W���i���j�܂�
�@���c�L�O���p�ق𑁂߂ɕЕt����� [;^J^]�A�����y�ɂȂ�B
 �ڎ��֖߂�
�ڎ��֖߂�
�@�������͈Â��ܓV�Ɩ��邢�ܓV�̂��傤�ǒ��Ԃ̓ܓV [;^J^] ���������A���ɂ͉����B
�@�P�T���ɎԂŏo�āA����̂m����̉��y�����ɁA�ăI�t�Ŏg���G���s��a����ɍs���B�V���Q�U���ɁA�����q�̉��ɁA�e�����������|�r�A�o�b�|�P�W�O�ƍ��킹�ĂR��A���̃}�[�`�ɏ悹�ĉ^�э��ނ̂ł��邪�A���߂ɐڑ����ĉ^�p�e�X�g�����Ă��������̂łˁB
�@�Q�S�U�����Ƃ����A�V���v���ȃR�[�X�B�i���y�����͊������ɂ���̂ł���B�jGoogle Maps �Ɉē������Ă�ƁA�u�����Ƒ����R�[�X��������܂����v�Ƃ������Ď�s���Ƃ������Ƃ��ɗU�����݂����Ȃ̂ŁA�v���� [;^J^]�B���̋����ŗL�����H���g���Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��̂��B[;^.^]
�@�P�U�F�S�T�ɒ������B�͂P�V�F�O�O�Ȃ̂ŁA���߂̃R�C���p�[�L���O�ɒ�߂��܂܁A���炭�J�[�X�e�łb�c�i�t�����N�́u������ �j�Z���v�j�����Ԓ����B�P�V�������O�ɉ��y�����ցB�G���s��a�����āA�߃���̎���ւƂ�ڕԂ�B�P�X���߂��ɋA��B
�@���̃G���s�Ƃo�b�|�P�W�O���A�l�h�c�h�}�[�W���[�̓��͑��ɐڑ����A�l�h�c�h�}�[�W���[�̏o�͑����e�����������|�r�̂l�h�c�h �h�m�ɐڑ����A����m�F�B�n�j�B
�@�������A���S�ł͂Ȃ��B���܂�ɐ��I�Șb�ɂȂ�̂łقڑS�ʓI�ɏȂ��� [;^J^]�A�e�����������|�r�̃V�X�e���R���g���[�����̐ݒ肪�A������̊��Ғʂ�ɋ@�\���Ă��Ȃ��B�����������A�Ȑݒ�����Ă݂��̂����D�D����́D�D�o�O���ȁB�e�X�g�P�[�X�������Ă����̂��B�Q�O�O�R�N�̐��i�Ȃ̂ŁA������[�ǂ����Ă��d�����Ȃ� [;_ _]�B�t�@�[���͍ŐV�i�ŏI�j�ł����� [;_ _]�B�N����A�e�����������|�r�̃e�X�g�ƃf�o�b�O�̐ӔC�҂͂�I[;_ _]�ʁi���O���� �� [;_ _][;^.^]�j
�@����[�Ȃ��A�^�p�ʼn�����邩�B[;^J^]�i�����������𑁂߂ɂ��Ԃ�o�����߂ɁA���߂ɃG���s����ɂ������̂�����A����̈Č��S�̂Ƃ��ẮA���҂ǂ���ɐi�s���Ă���̂ł���B[;^.^]�j
�@�����A�����B���N�W�U�B�����D�D
 �ڎ��֖߂�
�ڎ��֖߂�
�@���̉J�͏オ���Ă���B���V�B
�@�X�F�P�O�A�~�T���z�[���̊֘A�Ǝ҂��A���K�B�V�z�̂Q�R�����_���ł���B�X�F�T�O�A��Ɗ����B����������͂Ȃ��B

�@�l�b�g�Ï��X�ɔ������Ă����u�F�V���F��z���p�فv���͂����̂����A���́u�F�V���F��z���p�فv�����A���̂́u�F�V���F��z�����فv�ł����� [;^.^]�ʁi���ʐ^�j�B�������A�A�������B�����ɕԐM�A�u����ւ���Ă����̂ɋC�����Ȃ������v�Ƃ̂��ƂŁA���^�[�p�b�N�Ő��������e�i���́j�𑗂��Ă����Ƃ̂��ƁB
�@�ł��܂��D�D���������A�{��C�ɂ́i���܂�j�Ȃ�Ȃ��Ȃ� [;^J^]�B�܁A�X�ɂ́A�����O�̌��i���������肵�Ă��� ["^.^]�� �Ǝv�����A�i�����炭�X���Łj������o���ē��e���m�F���Ė߂��ԈႦ�Ă��܂����q�ɂ́A���������Ȃ��B�����āA���̎ʐ^�����߂Č��Ă݂ė~�����B���Ȃ��A�ԈႦ�Ȃ����M�A����H[;^.^] �ڂ�ῂ܂Ȃ��H[;^.^] �����āA�ǂ�������}�ЂŁA�ǂ�����ܒJ���m�҂Ȃ̂ł��� [;^.^]�B�����g�A�Ï��X�̓X���ł��̂Q��������ł���ƁA�ǂ��炪�ǂ��炩�킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł��� [;^.^]�B�߂��ԈႦ�Ă��܂������Ƃ��A����悤�ȋC������ [;^J^]�B����Ɍ����A���}�Ђ͓������ܒJ���m�҂ŁA�u�F�V���F���z���p�فv���o���Ă���̂ł��� [;^.^]�ʁB�ǂ��ł��A�u�F�V���F���z���p�فv�u�F�V���F��z���p�فv�u�F�V���F��z�����فv�D�D[;^.^][;^.^][;^.^]��
�@�P�Q�F�T�W�̃o�X�Ŕ��B����ƒ������� [;^.^]�A�P�S�F�S�Q�A���Ԍ����B�P�S�F�T�O�A���c�J���w���B�h����A�s����A�x����Ɨ��������B�����܂߂āA���������ȂЂł��̌ØV�t�@���ł���B�u���c�J���w�� �J��30���N�L�O�m�Y���@�̐��E�W�`�w�U�k�@�����x�Ƒn���̋O�Ձ`�v�i�`�W���P�V���i���j�܂Łj�ƁA�u�C��\�O�Ɠ��{SF�v�i�`�X���Q�W���i���j�܂Łj�B�ʐ^�B�e��������Ă���̂́A�O�҂̂݁B



�@�u�r�e�j�Ǝm�Y���@�v�Ƃ����p�l���́A��ϖʔ����B




�@�~�铃�����������A���ǂ��Ă������������B
�@�u�C��\�O�Ɠ��{SF�v�W���A�Ȃ��Ȃ��ʔ����B�܂��܂�����͂���̂ŁA�������E�߂��Ă����B
�@�P�U�F�R�T�ɏo��B�S�l�ŐV�h�́u�����q�v�ցB�P�V�F�S�O�A�T�l�ڂ̂g����́A���ɗ����Ă����B�v�X�̈��݉�ł���B
�@�o���b����v���o����͈͂ŏ����Ă����ƁD�D�Ö{�A�f��A�u�����C�g�v�A���[�v���́A�uAll You Need is Kill�v�B�f���m�y�́i�M��j�^�C�g���B�܂炯�A�`�h�B�u�������������v�B�u�{�v�̔}�͎̂�����d�q�Ɉڂ���邪�A�d�q�u�b�N�́u�w���v���Ă��u���L�v�ł���킯�ł͂Ȃ��B�u�ǂތ����v���Ă��邾���ł���A���̌����͋ɂ߂Ă����Έ���I�ɒD���Ă���B�u�Ö{�v�Ƃ����T�O���Ȃ��B
�@�`�h���쐬�����������ǂ������ׂ邽�߂̂`�h���A���R���ɑ��݂��Ă���͂��B�ƂȂ�ƁA�`�h���m�̔��S���i�u�����������Ƃ������Ƃ͓����ɂ��Ƃ��Ă���v�j���A���ɔ������Ă��邩������Ȃ��B
�@�P�X�F�T�O�ɔ��B�������悤�Ȃ��N���ł͂Ȃ� [;^J^]�B�V�h�w�ɖ߂���R���U�B�Q�O�F�P�U�̍鋞���ŁA�߃���ɒ��s�B�Q�P�F�O�S�A���B�Q�P�F�Q�O�̃o�X�ŁA�Q�P�F�R�O�߂��ɁA�A��B
 �ڎ��֖߂�
�ڎ��֖߂�
�@���āA�V���T���͏I����Ă���̂����A�������A�����Ƃ��N����Ȃ������B������O�ł���D�D�Ƃ͂����A���̑����ŃC���o�E���h�ƊE�𒆐S�ɐ��牭�~�̌o�ϑ��������������炵���A�u�܂��ɑ�ЊQ���v�ƌ�����܂��������̂Ƃ���B�V�����ɂȂ�Ȃ���Ȃ��D�D
�@���Ȃ݂ɁA�u�O�ꂽ�̂ł͂Ȃ��B�u�V���̂T���v�Ƃ����̂́A�ҏW�҂ɂ��u�V���̂����v�̕����ԈႢ�ŁA�܂�A�V���R�P���܂ł͗\���͈͓̔��ł���v�D�D[;^.^] �P�X�X�X�N���ɂ��A���̂悤�ȋY�������悤�ȋC�����邵�A�u���͂W���ł����v�Ƃ��Ȃ�Ƃ��A�������Ȃ��Ȃ�܂ł��炭�S��̂��낤�B
�@�܁A�ނ���u�ǂ������T���v������ƁD�D������ɐU���s���ɉՂ܂�Ă���̂ł��낤�i�P�X�X�X�N�̋L�����Ȃ��j�Ⴂ���ソ���ւ́A�u�\���Ƃ����̂͂��̂悤�Ȃ��̂��v�Ƃ���������ʁB����ƁA�u�o�J�Ȃ͓̂��{�l�����ł͂Ȃ��A�\���Ƀo�J�ȊO���l���\���ɑ吨����v�Ƃ������Ƃ��A�������ꂽ�Ƃ������ƁB�O�q�̌o�ϑ����̌�������̂ŁA�u�ǂ������T���v�Ƃ����ƌꕾ������̂ł͂��邪�D�D[;_ _]
�@ChatGPT �ɁA�u�������������̑����ɂ��āA�_�]���Ă��������v�ƁA�u���Ă݂��i�� ���j�B���ɑÓ��Łu�䂪�ӂ���v�ȓ��e�ł���̂����A���ꂪ�����B�����������Ԃ��Ă���Ɩ������āA���e�������邱�Ƃ��Ȃ��A����ȏ㎩���ōl���邱�Ƃ��ȗ����Ă��܂��D�D
 �ڎ��֖߂�
�ڎ��֖߂�
 ��T��
��T��
 ���T��
���T��
 ���
���
 �q�c�킽��̃~�N���R�X���X�ւ̔�
�q�c�킽��̃~�N���R�X���X�ւ̔�
Last Updated: Jul 10 2025
Copyright (C) 2025 �q�c�킽��
Mail [KurataWataru@gmail.com] Home [http://www.kurata-wataru.com/]
 2025�N06��30���F���z���p�I�����r���[��������
2025�N06��30���F���z���p�I�����r���[��������
 2025�N07��01���F�~���W�^����}���ف^�Ï��h���X
2025�N07��01���F�~���W�^����}���ف^�Ï��h���X
 2025�N07��02���F���u�P�O�O�\���@�͈�i��
2025�N07��02���F���u�P�O�O�\���@�͈�i��
 2025�N07��03���F�V�`�W���̓W����ϗ��\��
2025�N07��03���F�V�`�W���̓W����ϗ��\��
 2025�N07��04���F�G���s��a����
2025�N07��04���F�G���s��a����
 2025�N07��05���F���c�J���w�ف^�ØV�̏W��
2025�N07��05���F���c�J���w�ف^�ØV�̏W��
 2025�N07��06���F�ꕾ�͂��邪�D�D[;_ _]
2025�N07��06���F�ꕾ�͂��邪�D�D[;_ _]










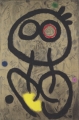





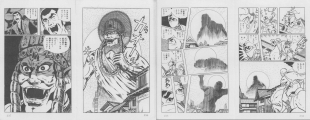

 ���c�L�O���p��
���c�L�O���p��







 �q�c�킽��̃~�N���R�X���X�ւ̔�
�q�c�킽��̃~�N���R�X���X�ւ̔�